【GF00089】マカロンのようなかわいい亀頭に大注目しちゃうオナニー|涼真
品番:GF00089サンプル動画
オープン記念!!期間限定!!
今だけ新規登録でフル動画を全て無料視聴
涼真の下半身は、すでに何も隠していなかった。淡くピンクがかった亀頭が、張り詰めた肉棒の先でわずかに濡れ、まるで何かを訴えるように艶を放つ。そんな自分の姿にさえ欲情しながら、彼はあえてゆっくりと、焦らすように肉棒を擦り始めた。
自撮りオナニーの興奮はいつも射精感を早めてしまう
最初はじれったいほどのリズム。だが、透明なお汁が先端からにじみ出し始める頃には、身体は正直に反応しはじめていた。吐息が漏れ、擦る速度も自然と上がっていく。意識の奥がしびれるような快感に包まれ、涼真はもう、耐える理由を見失っていた。
クライマックスは唐突で、けれど避けられない。鮮度の高そうな白濁が、鋭く跳ねるように放たれ、熱と一緒に空気を切り裂いていく。すべてを出しきったあとも、涼真の指は止まらなかった。ほてりが残る亀頭をゆっくりと撫でながら、静かな余韻を贅沢に味わっていた。
サンプル画像
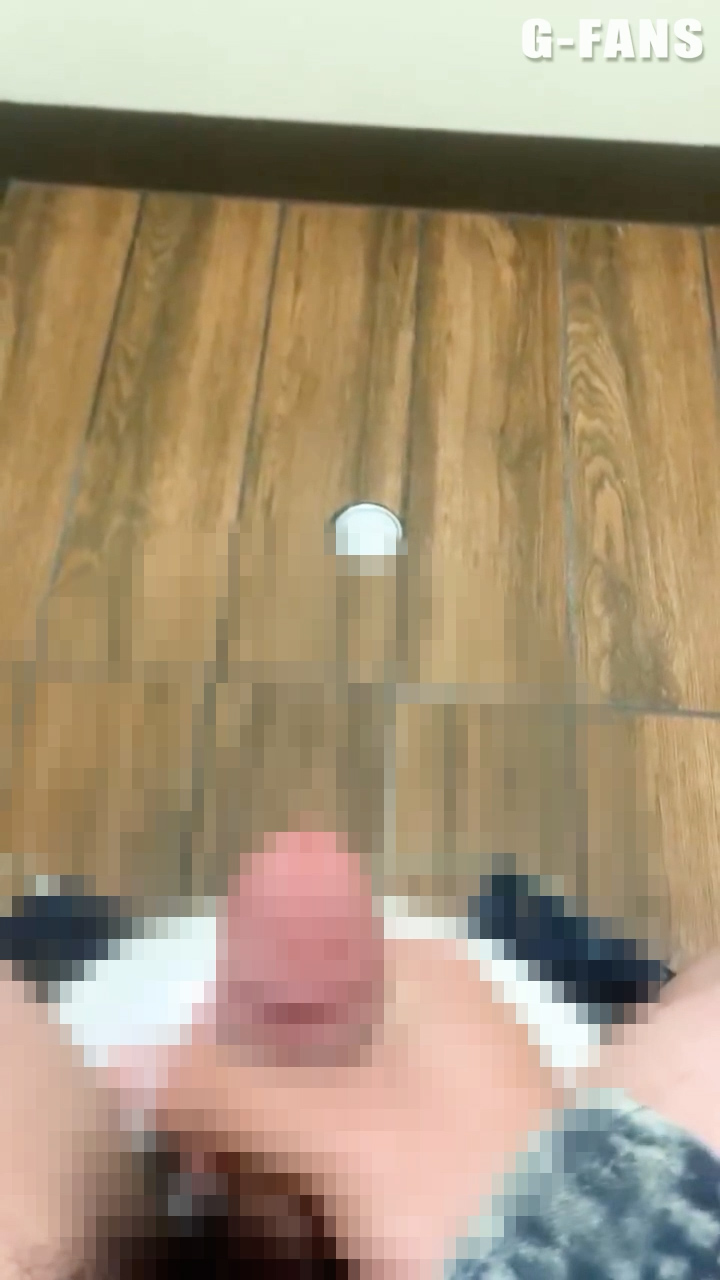

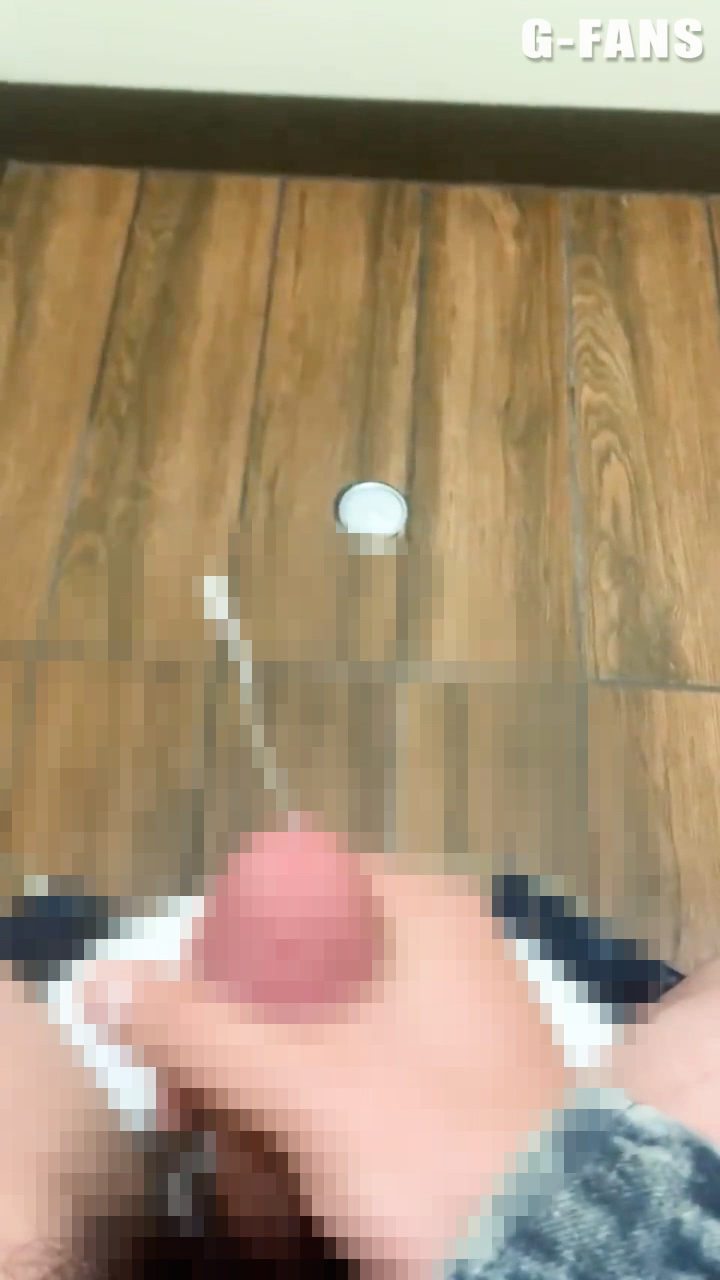
.静止画003のコピー-225x300.jpg)



