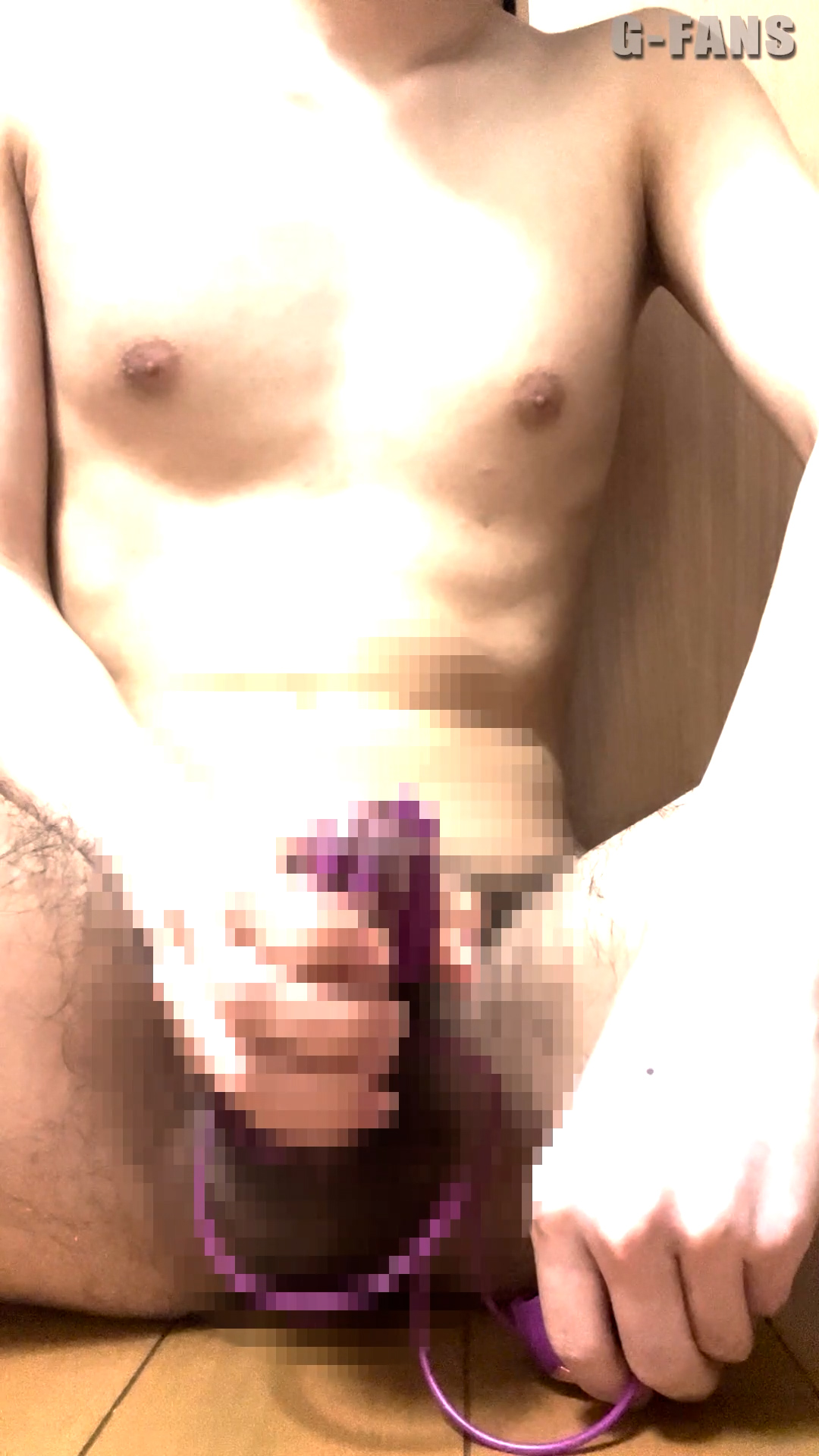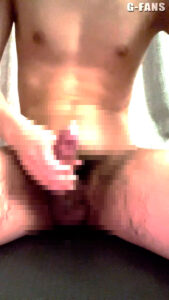【GF00042】ローターで竿と亀頭を刺激して漏れる声|HARU
品番:GF00042サンプル動画
オープン記念!!期間限定!!
今だけ新規登録でフル動画を全て無料視聴
熱を帯びた指先が下腹部に触れるころには、すでに陰茎はいきり立ち、誇らしげに天を突いていた。妖艶なパープルのローターを手に取り、肉棒の左右から挟み込むようにセットする。スイッチを入れると、低く唸るような振動が根元にじんわりと広がり、ゆっくりと全体を包みこんでいった。
ぷっくりと充血した亀頭にも、その振動は容赦なく届く。上下から挟み込むようにローターをずらせば、鋭く甘い刺激が一点に集まり、身体がわずかに跳ねる。「ん…あ…」と、情けなく切なく漏れる吐息が、室内の空気を熱く変えていく。
快感が頂点に達したそのとき、こすられていないにもかかわらず、熱は一気に開放へと向かう。手を止める間もなく、白濁が震える亀頭からほとばしり、彼はただその余韻の中で、静かに震えていた。快楽は、触れることだけがすべてではないと知る、濃密な瞬間だった。
サンプル画像